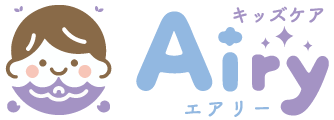”キッズケアAiryこまき” の児童発達支援・放課後等デイサービスにおける計画(支援プログラム)は、以下の通りとなります。
更改日:令和7年1月22日
事業所理念
お子さまとの出会いを大切に日々共に成長し、笑顔あふれる心地よい空間(Airy)創りを大切にします。
優しく子供たちに寄り添い、成長を支え、家族のように安心できる関わりを提供します。
支援方針
明るく温かい雰囲気の環境の中で、友達との交流や、スタッフと安心できる関係性を構築し、関わり・心地よさ・楽しさを味わえるように支援し、安全安心に笑顔でAiry(エアリー)で過ごせるように支援していきます。
日々の活動が今後の成長の礎になるように保健的で安全な環境を整え、身体及び五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)の機能を伸ばしていく療育活動を行っていきます。
支援内容
■児童発達支援
営業時間・送迎の有無
営業時間 9時 ~ 18時まで / 送迎 あり
支援内容詳細
| 本人支援 | 健康・生活 | ・ご利用前に保護者さまご協力のもと「健康チェックシート」の記入をお願いしていています。施設に到着した時午前中と、午後に検温と視診を行います。 ・SpO2、心拍数、血圧などの測定をし、常に健康状態を把握しながら安心して過ごせるように支援していく。 ・日常生活の基本的生活スキルの自立の為に、視覚や聴覚に働きかけて状況を理解できるように工夫して支援していく。 |
| 運動・感覚 | ・五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)に働きかけるような療育活動を行っていく。実際に本物を使用して五感に刺激を与えていけるように工夫する。 ・同じ姿勢でいることが多い時は、クッションやタオルなどを使用し、適切なポジショニング、姿勢ケアや体位変換を行ない快適に過ごせるように心掛ける。 ・療育活動やあそびの中で、身体の動かし方、力加減を習得できるように工夫して支援していく(リハビリの楽しさや出来た時の喜びを持ってもらえるように取り組む。) ・外出や○○体験などを取り入れ、お家でできないような体験ができるように年間計画を立てていく。 ・お散歩に行き、外気浴をして気分転換をしていく。 | |
| 認知・行動 | ・積極的に療育活動に参加し、関心を持って興味が広がるようにしていく(興味が出てくる→自分でもやりたいという意欲が湧いてくる→できる喜び→できることが増えてくる。) ・行動切り替えなどを認識できるように、聴覚・視覚でも分かりやすいように支援していく(場面切り替えの音楽を決めて流す。場面切り替えを絵(時計・行動図)にして表示する。) | |
| 言語・コミュニケーション | ・コミュニケーションの基礎的能力の向上と、手段の幅を広げていけるように支援していく。(表現が指差しや、手を使ったサインなど見逃さず、繰り返し職員が一緒に使い、時には新しいサインを提案し、表現の幅を広げていけるように工夫していく。) ・非言語的コミュニケーションのお子さまには、場面に応じたジェスチャーや仕草、表情を繰り返し伝えてコミュニケーションを取っていく。 | |
| 人間関係・社会性 | ・他児とのコミュニケーションが苦手なお子さまには、気持ちが表現できるように伝えたい気持ちを大切にして、気持ちを汲み取りながら職員がコミュニケーションの架け橋を担っていくように心掛けていく。 ・色々な活動や体験を通して、集団生活のお約束やルールを守っていくことを知ってもらう為に、声掛けや視覚で分かりやすく支援していく。 | |
| 家族支援 | ・送迎時に丁寧なコミュニケーションを心掛け、保護者さまとの関係性を築いていく。 ・年に2回の個別面談を実施し、ご家族の生活状況やお困りごとを聴取する機会を作る。 ・Airy(エアリー)での活動の様子を日々の記録や、LINEでお伝えする。 | |
| 移行支援 | ・将来を見据えた地域の生活の場や、育ちの場との交流と情報共有。 ・将来に向けての進路や移行先の選択についての家族への相談援助や、移行に向けての様々な準備支援。 | |
| 地域支援・地域連携 | ・関係機関との情報共有を図り、必要に応じて助言をうけながら支援に取り入れていく。 ・将来に向けて地域福祉・関係機関との関係を築いて、本児が安心して過ごせるように支援する。 ・地域連携会議等へ積極的に参加していく。 ・保育園、幼稚園へ訪問を行い、情報共有していく。 | |
| 職員の質向上 | ・職員の各種勉強会や研修への参加(社内・外部) ・資格取得の支援あり。 | |
| 主な行事等 | ・1月→お正行事・初詣、2月→節分、4月→お花見、3月→ひな祭り、4月→春の遠足、5月→節句、7月→プールあそび、8月→夏祭り、9月→お月見会、10月→ハロウィン、11月→紅葉・秋狩り・秋の遠足、12月→クリスマス ・毎月お子さまの誕生日会を行っている。 ・社会見学、お買い物体験、絵本図書館、マルシェへお出掛け、食育プログラム、施設や公園のお出掛け、畑作業(作物の収穫)。 | |
■放課後等デイサービス
営業時間・送迎の有無
営業時間 9時 ~ 18時まで / 送迎 あり
支援内容詳細
| 本人支援 | 健康・生活 | ・学校でのお子さまの引き渡し時に、学校生活でのご様子をお聞きして、放課後等デイサービスでの過ごし方をスムーズに移行出来るように情報共有を行う(トイレ、お昼寝等) ・ご利用前に保護者さまご協力のもと「健康チェックシート」の記入をお願いしていています。施設に到着した時午前中と、午後に検温と視診を行います。 ・SpO2、心拍数、血圧などの測定をし、常に健康状態を把握しながら安心して過ごせるように支援していく。 ・日常生活の基本的生活スキルの自立の為に、視覚や聴覚に働きかけて状況を理解できるように工夫して支援していく。 |
| 運動・感覚 | ・五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)に働きかけるような療育活動を行っていく。実際に本物を使用して五感に刺激を与えていけるように工夫する。 ・同じ姿勢でいることが多い時は、クッションやタオルなどを使用し、適切なポジショニング、姿勢ケアや体位変換を行ない快適に過ごせるように心掛ける。 ・療育活動やあそびの中で、身体の動かし方、力加減を習得できるように工夫して支援していく ・リハビリの楽しさや、出来た時の喜びを持ってもらえるように取り組む。 ・外出や○○体験などを取り入れ、お家でできないような体験ができるように年間計画を立てていく。 ・お散歩に行き、外気浴をして気分転換をしていく。 | |
| 認知・行動 | ・積極的に療育活動に参加し、関心を持って興味が広がるようにしていく(興味が出てくる→自分でもやりたいという意欲が湧いてくる→できる喜び→できることが増えてくる。) ・活動に参加することで興味が広がり、出来ることが増えて、自分自身で出来ることが認識できるように支援、声掛けを工夫する。 ・行動切り替えなどを認識できるように、聴覚・視覚でも分かりやすいように支援していく(場面切り替えの音楽を決めて流す。場面切り替えを絵(時計・行動図)にして表示する。) | |
| 言語・コミュニケーション | ・コミュニケーションの基礎的能力の向上と、手段の幅を広げていけるように支援していく。(表現が指差しや、手を使ったサインなど見逃さず、繰り返し職員が一緒に使い、時には新しいサインを提案し、表現の幅を広げていけるように工夫していく。) ・非言語的コミュニケーションのお子さまには、場面に応じたジェスチャーや仕草、表情を繰り返し伝えてコミュニケーションを取っていく。 | |
| 人間関係・社会性 | ・色々な年代の他児と関わりを持てるように異年齢交流の場面を設けて、交流においてのコミュニケーションで社会性・人間性を築いていけるように支援していく。 ・他児とのコミュニケーションが苦手なお子さまには、気持ちが表現できるように伝えたい気持ちを大切にして、気持ちを汲み取りながら職員がコミュニケーションの架け橋を担っていくように心掛けていく。 ・色々な活動や体験を通して、集団生活のお約束やルールを守っていくことを知ってもらう為に、声掛けや視覚で分かりやすく支援していく。 | |
| 家族支援 | ・送迎時に丁寧なコミュニケーションを心掛け、保護者さまとの関係性を築いていく。 ・年に2回の個別面談を実施し、ご家族の生活状況やお困りごとを聴取する機会を作る。 ・Airy(エアリー)での活動の様子を日々の記録や、LINEでお伝えする。 | |
| 移行支援 | ・将来を見据えた地域の生活の場や、育ちの場との交流と情報共有。 ・将来に向けての進路や移行先の選択についての家族への相談援助や、移行に向けての様々な準備支援。 | |
| 地域支援・地域連携 | ・関係機関との情報共有を図り、必要に応じて助言をうけながら支援に取り入れていく。 ・将来に向けて地域福祉・関係機関との関係を築いて、本児が安心して過ごせるように支援する。 ・地域連携会議等へ積極的に参加していく。 ・学校からの引き渡しの時に、先生とコミュニケーションを取り、情報共有を行う。 | |
| 職員の質向上 | ・職員の各種勉強会や研修への参加(社内・外部) ・資格取得の支援あり。 | |
| 主な行事等 | ・1月→お正行事・初詣、2月→節分、4月→お花見、3月→ひな祭り、4月→春の遠足、5月→節句、7月→プールあそび、8月→夏祭り、9月→お月見会、10月→ハロウィン、11月→紅葉・秋狩り・秋の遠足、12月→クリスマス ・毎月お子さまの誕生日会を行っている。 ・社会見学、お買い物体験、絵本図書館、マルシェへお出掛け、食育プログラム、施設や公園のお出掛け、畑作業(作物の収穫)。 | |